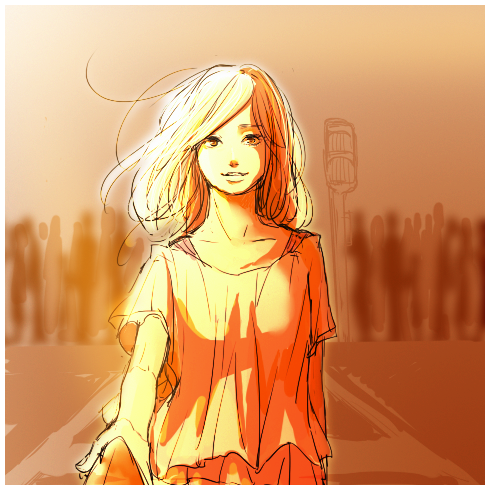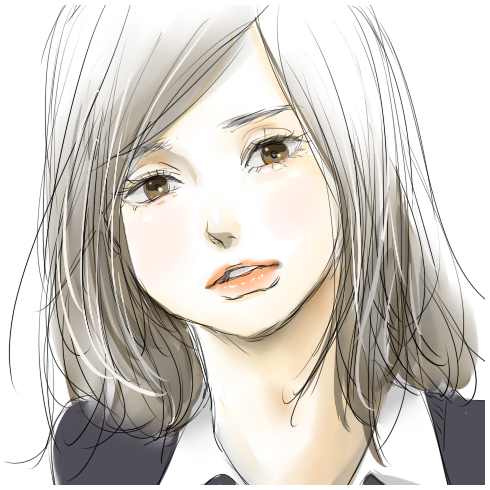俺が女の子たちを殺してわかったこと 第一夜『俺が最初に殺した女の子』
◆
意識とは無関係に肩が震えた。奇怪な音が喉の奥で鳴る。
胸を焼くような強烈な不快感に耐え切れず、俺は戻してしまった。
便座に手をついて、俺はひたすら吐いた。
逆流した胃液が口の中に広がって、視界が涙でにじむ。
「なんで俺は……」
網膜に焼きついたヤエの死体は、一向に消えない。
結局俺は一時間以上、ひたすら胃液を吐きつづけた。
吐き気が収まっても、しばらく俺はその場から動けなかった。
手足に力が入らない。
まぶたが熱い。そう思ったときには涙があふれる。
いったい俺はこれからどうすればいいのだろうか?
警察に行くか?
それとも救急車……そこまで思考して俺は首を振った。
俺の脳は異常な事態に疲弊し混乱しきっていた。
まず俺はなにからしなければならない?
やはり一番最初にするのは死体の確認だろうか?
いや、それ以外になにをする?
もしかしたらまだ彼女が生きている可能性があるか?
俺はずっとワルイ夢を見ているだけかもしれない?
彼女が死んでいたら俺はどうする?
やはり警察に行かなければ?
だが、アレはほとんど事故だ。俺の意思なんてなかった。
じゃあ隠蔽するか?
推理小説のように?
できるのか?
頭の芯はもはや麻痺して、満足な思考もできなかった。
ふらふらと立ち上がって、トイレを出る。
短い廊下を歩いて、彼女の部屋へと入った。部屋の中は真っ暗だった。
俺はいつの間に明かりを消したのだろうか?
「うぅっ……」
むせ返るような血のにおいが部屋に充満していた。
さっきまでは気づけなかったが、血のにおいとはこうも強烈なのか。
俺は目を凝らした。明かりをつける勇気はなかった。
だが見当たらない。
おかしい。血だまりは存在するのに肝心の彼女のからだがない。
俺が包丁で刺して殺した、あの子がいない。
実は彼女は死んでいなかった?
生きていた?
では彼女はもしかして外へ行ったのか?
なんのために? 警察を呼びに? 救急車を呼びに?
不意に玄関ドアが開く音がして、俺は飛び上がりそうになった。
蝶番が悲鳴のような音を上げる。
もしかしたらその音は、俺の心の叫びだったのかもしれない。
靴を脱ぐ音。足音が近づいてくる。誰だ?
誰だ?
泥棒?
警察?
それとも――
俺は動けない。
この場から逃げなければいけないのに、足はこおりついてしまっている。
廊下と部屋を隔てていた扉が開く。
最初、その人影が誰かわからなかった。
だが、その人影が明かりがつけるとすぐ誰かわかった。
わからないわけがなかった。
「ビビりすぎだろ、お前」
扉から現れたのはヤエだった。
ヤエが唇のはしをめくりあげた。
「なんで……」
「あ?」
「な、なんで生きてる……?」
声がみっともなく震える。とてもじゃないが、普通に声を出せるような状況じゃなかった。
「なんでって……お前、『ヤエ』が言っていた言葉を忘れたのかよ?」
恐怖に麻痺した脳みそでも、目の前の女の子の様子がおかしいことは理解できた。
「ヤエが言っていた言葉?」
「『わたし、死んでも死なないの』。アイツはそう言わなかったか?」
思い出せない。たしか言っていたような気もするし、言ってなかったような気もする。
「まあこんな状況で普通に会話しろっていう方が無理か」
ヤエがまた笑った。唇のはしが耳にまで届きそうな、独特の笑い方だった。
「ちなみに今までどこにいたのかというと、コンビニ行ってたんだよ。腹が減っちまってさ」
「き、キミはヤエなんだよね?」
ヤエであるはずの女の子が、口を開けば開くほど、俺の中で違和感のようなものが広がっていく。
おかしい。彼女はこんな口調じゃない。
まるでヤエのからだを使って別の誰かが、話をしているようだった。
ヤエはケロッとして言った。
「当たり前だろ。今のアイツは死んでるんだから」
「どういうこと」
「なんていうのかな、強いて言うならアイツとはちがう別人格、みたいな?」
「……」
理解ができない。なにをこの子は言っているんだ?
だがひとつ、確かなことがわかった。
『わたしは死んでも死なないの』
この言葉は間違いなく本当だったということだ。
今日はここまで
>>47の人絵うますぎてびっくり
ありがとうございます
この調子でダラダラ続けます
本気過ぎワロタ
オープンもそろそろ>>1みたいな実力者がちょいちょい現れる頃だな
ありがとうございます!勝手にすみません。。
ヤエちゃん魅力的です
59-60
ありがとう
お絵かきは私が勝手にやったので1さんの許可なしです
ごめんなさい
また明日楽しみに読みに来ます!
1さん頑張ってください!
1さんが大丈夫だったら描きたいかも。。(*´ω`*)
期待
再開
>>61
ときどきホラーssを書いてる
>>66
ご自由に。とか言ってるけど、正直また書いてほしかったりする。
「キミはなんなの?」
「なんなのって、なにが?」
「キミは本当に人間なの?」
「人間じゃないなら、なにに見える?」
ヤエの眉が少しだけつり上がった。
まるで威嚇する猫のように、目を細める姿はやはり彼女であって彼女じゃない。
「だって……俺はたしかにキミの腹を刺した。そうだ、床に血だって……」
俺はカーペットを指さした。シミはすでに変色し始めている。
「たしかに普通の人間って主張するのは、かなりつらいかもな」
「じゃあキミは……」
「見た目はそのまま、見ての通り人間だ。でも、死なないんだ」
「いや……」と彼女はそこで口もとに手を当てて、「ちがうな」
「死ぬんだ。でも、死んでもいかなる理由か生き返るんだよ」
「親は……?」
「親はいるにはいる。でも詳しくは知らない」
さらにヤエは続けた。
「今まで色んな家に世話になった……のかな? そこらへんは覚えてないな。
でもまあ最終的には、一人暮らしをしてるわけだ」
「ヤエ。キミは普通に生まれてきたのか?」
「普通って?」
「だから、親から生まれてきたのかって……」
「さあ?」
「さあって……」
「記憶が曖昧なんだ。つーか、わたしのことよりもっと重要なことがあるだろ」
ヤエは苛立たしげに髪を乱暴にかいた。
彼女の正体を知る以上に重要なことが、俺には思いつかなかった。
「これからの話に決まってるだろ。お前、これからどうするんだよ?
一回、殺してくれたけどさあ」
ヤエが俺に近づいてくる。
息のかかる距離。無意識に俺は後ずさる。
そう、ヤエの正体がどうであれ俺は一回彼女を殺している。
殺人は犯罪だ。そんなことは子どもでも知っている。
「これを見てみな」
ヤエが服の裾をめくりあげた。真っ白で瑞々しい肌がやけにまぶしい。
僕は知らず知らずのうちに息を飲んでいた。
肉付きの薄い腹には、傷ひとつなかった。
「傷が……ない」
だったらこのカーペットを濡らした血は、いったいなんだったんだ?
「まあ見ての通り、傷なんてひとつもないわけだ。なかなかキレイだろ?」
ヤエが再び唇をつりあげる。
もし、こんな状況じゃなかったら俺は、どんな行動に出ただろう。
女の子とふたりっきり。
狭い部屋。
音のしない夜。
恋愛ドラマにでも出てきそうなシチュエーションだった。
ドラマとちがうのは。
目の前の女が異状で。
部屋の中は血の匂いで満ちていて。
俺が人殺しだってことだ。
「お前は人殺しを一度実行している。
でも証拠はないし、そもそも人殺しそのものが成立していない。でもさあ」
胸ぐらをつかまれて息が少し詰まった。彼女の顔が近くなる。
真っ黒な瞳には、引きつった表情の俺が映っている。
「お前は自分がなにをしたか、自分で理解してるよなあ?」
「ど、どうすればいいんだよ?」
「ヤエが言っていたことを思い出せよ。そうすりゃおのずと答えは出るだろ」
いまだに頭の中は混乱しきっていた。
息苦しさにみっともなく喘ぐ俺に、ヤエは呆れたようにため息をついた。
「わかんねえかなあ」
「こんな状況なんだ。考えがまとまらないんだよ」
「殺せって言ってるんだよ」
「……」
「わたしを殺せ。ヤエだってそう言ったはずだ」
「死なない人間をどうやって殺すんだよ」
「それを考えろって言ってんだよ。それぐらいわかれ、ボケ」
ヤエが俺のシャツの胸もとから、手をはなす。
よく見れば、ヤエの手首は異様に細かった。
「一度殺したんだ。だったら二度殺すのも、三度殺すのもちがわねえだろ」
「そ、そんなことない!」
気づいたときには叫んでいた。ヤエの眉がぴくりともちあがった。
『彼女』の面影がよぎった気がしたが、それも一瞬だった。
「一回目の殺しはほとんど事故だ! でも次からやる殺しは、意識的にやるってことだろ!?
そんなのはダメだ! 人殺しだぞ!?」
「なんでダメなんだ?」
あすの天気を聞くような調子で言われて、俺は言葉に詰まった。
彼女を言い負かそうと、俺は殺しというものについて、なんとか論理的に考えようとした。
そんな俺の思考をさえぎるようにヤエは吐き捨てた。
「くだらない。人殺しがどうだとか、そんなことはどうでもいいんだ。
そもそも人殺しなんて、どんな理由があろうがダメだ。
それにそんな一般的な考え方が、死なないわたしに当てはまるわけないだろ?」
普段思っていることに近いことを言われた。
「まあでも、お前頭悪そうだもんな。わたしを殺せない人間といても仕方ないか」
ヤエの顔から表情が消えた。
なぜか焦燥感にも似たものを感じて口を開いていた。
「ま、待ってくれ」
「なんだ?」
「ヤエ……キミも死にたいの?」
「このからだには色んな人格が潜んでいる」
ヤエが自分の胸を人差し指でさす。やけに胸元が開いたTシャツ。
鎖骨の影に俺は目を奪われかけた。
ここにきて俺は初めて、彼女が服を着替えていることに気がついた。
「確かなのは、からだが死ぬと人格が入れ替わるってことだ。
逆を言えば、それ以外はなんもわからないんだけどな」
「人格が入れ替わる……」
俺はヤエの言葉を理解するために復唱した。
もっとも、血の匂いで錆びてしまった脳の芯は、彼女の言葉の半分も咀嚼できてないようだった。
「そう。そして、わたしも完全には把握してない。
だけど、たぶんみんな死にたがっている」
「だから殺せってこと?」
「そうだ。……いや、べつに殺さなくてもいい。
わたしが復活しない殺しの手段を考えてくれりゃ、それでいいんだ」
ヤエがベッドに腰かける。
話の内容とは裏腹に彼女の口調は実に軽い。
「そうは言っても、今のお前の状態じゃあ気の利いたアイディアも出せなさそうだ」
ヤエはあくびをした。
「とりあえず眠いし、寝るわ。お前も寝たけりゃ寝ろ」
彼女が横たわってから、眠るまでの時間はあまりに早かった。
規則正しい寝息が耳に入ってくると、俺の足は軟体動物のように力が抜けていた。
カーペットの赤いシミに足もとが沈む。
自分がとんでもないことに、首を突っ込んでしまったということだけは認識できていた。
「また、殺す……」
出てきた言葉はひび割れている。口の中はかわききっていた。
ひざをついたカーペットは、まだ血で濡れていた。
◆
自分がまだ人殺しをするなんて、わずかたりとも思っていなかったころ。
今思えば、あのときの俺はなんて平和な生活をしていたんだろうと、心からそう思った。
「相変わらず小食だね。もっと食べないの?」
ばあちゃんの言葉に俺は首をふった。
この家の食事が俺は嫌いだ。
まずいわけではない。ただ、この家のごはんは、噛みごたえがまったくないのだ。
米もそうだ。びちゃびちゃして気持ち悪い。
一度、自分好みで固めに炊いたら、文句を言われた。
「たまには脂っこいもんが食いたいな」
俺はわざとらしくそう言った。
「肉じゃがの豚肉があるでしょ」
「こんなんじゃあ、全然ジューシーじゃないよ」
席を立って食器を運ぶ。
自分の使ったものを洗って、「ごちそうさま」とだけ言って俺は自分の部屋に戻った。
この家のごはんは嫌いだ。
だが、なにより嫌いなのは食事中にまとわりつく得体の知れない空気だった。
おばさんとばあちゃんが基本的にしゃべって、ときどき俺がその会話に参加する。
母さんはもくもくと口を動かすだけ。
ほこりっぽい食卓は俺にとって、ただ苦痛なだけだった。
「あっ……」
ケータイを開くとヤエからメールが来ていた。
内容は週末のデートについてだった。
食事によって胃に溜まった憂鬱が、いっきに晴れた気がした。
俺はメールの文面を考えるために、ベッドに寝転んだ。
つづく
いったいこの娘をどうやって殺すのか
次回も楽しみにしてます…!
メガテンっぽい
上のまとめられてるから見たけど、この絵自分のものみたいに使うのはちがくね?善意で描いてもらってんだし
転載禁止前のvipとここなんかに書く時点で転載オッケーって言ってるのと同じ
冗談で言ってるのか?
荒らしかなんかだろ
ほっとけ
本人らがいいならそれでいいじゃん
好きで描いたんだから気にしないし、1さんのブログで
感謝って言ってくれてたよ~、嬉しかったですよ。
荒れる原因になりそうなら辞めておこうかな。
>>98
ありがとう!
>>104
メガテン好きなのバレたw
>>106
ありがとう、でももう辞めとく!
やだー良い場面を挿絵みたいにたまに書いてほしいなーと期待してたのにー
書いてよーう
あと>>1blogあるのか
挿絵とっても素敵でした有り難う!
1も108も(復活してくれたら)コテつけてほしーなー
ちびりそうなほど絵が怖いけどww