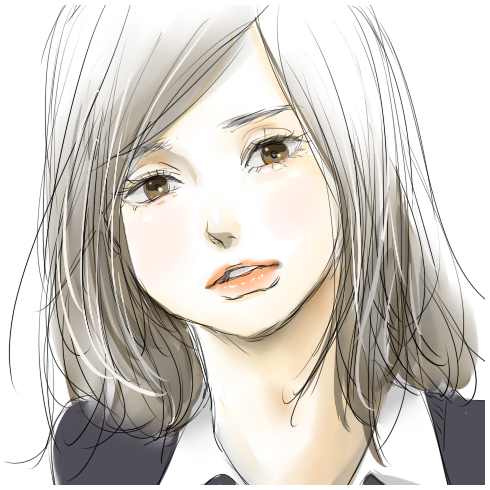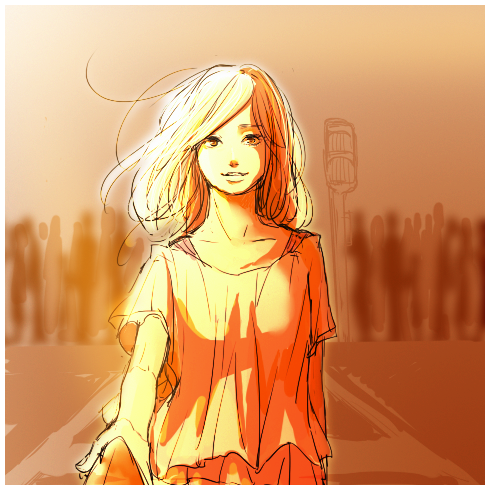『なぜ人を殺してはいけないのか?』
おそらく、誰もが一度は考えることじゃないかな。
でも俺はこの手の疑問は嫌いだ。
完璧な答えが存在しないし、結局考えるだけムダだから。
『法律で禁止されているから』
だからそれだけで理由は十分だと思う。いや、そう思っていた。
でも実際に人を殺した俺だからこそ言えることかもしれないけど。
『なぜ人は人を殺すのか』
あるいは。
『なぜ人は生きようとするのか』
このふたつについては、もう少し人間はよく考えるべきなのかもしれない。
自分によりかかってくる死体のぬくもりが冷えていくのを感じながら、俺はそんなことを思った。
俺が最初に殺した女の子の名前はヤエ。
彼女の第一印象をなにかと聞かれたら、『真っ白』と俺は答える。
とにかく肌の色が白い女の子だった。
誇張でもなんでもなく、生まれてこの方、陽の光を浴びたことがないのではと思ってしまうぐらい色白だった。
俺が見てきた人間の中で、ゆいいつ儚いという言葉が似合う女の子。
だから日差しのもとに彼女が出ると不安になった。
太陽の光に溶けて消えてしまうのではないかと、ありえない妄想を何度かしたことがある。
だけど、性格に関して言えば儚さからは程遠いかった。
明るい。真面目。活発。ポジティブ。何事にも積極的。
ヤエは絵に書いたような模範的な生徒だった。
彼女が教師に怒られた場面など見たことがない。
しかしここまで語っておいてなんだけど、俺は彼女についてそこまで詳しいわけじゃない。
だから、たまたま下校中にヤエと帰っているとき、
「私を殺してくれない?」
と笑って言われたときは、彼女が本気かどうかさえ判断できなかった。
まず殺す理由がないだろ。
食べるわけでもないなら
「冗談かなにか?」
「わたし、こういうことは冗談では言わないようにしてるの」
「本気で言ってるってこと?」
「もちろん」
「……理由は?」
「理由?」
「そう。どうして死にたいの?」
「死にたいって思うのに理由がいるの?」
語尾があがると、いっしょに彼女の眉が少しだけあがった。
本気で俺は言葉に詰まった。
「そりゃ理由がいるだろ。人を殺すにしたって、人に殺されるにしたって」
普段思ってることとは、真逆のことが口をつく。
「そもそも死にたいなら、人に頼るなよ」
「自分で死ねるなら、わたしもそうしたいんだけどね。死ねないの」
「は?」
「わたし、死んでも死なないの。だから、誰かが殺してくれないとダメなの」
隣を歩くヤエの口調はいたって真面目で、俺は言葉を失った。
なんでこんな会話の流れになったんだ?
ああそうだ。
たまたま校門前で鉢合わせして、一緒に帰ろうって流れになったんだ。
で、今日やった授業の話になった。たしか、家庭科の授業について。
一人暮らしにどれだけの金が必要かって話になって、その流れで自分の家の話になった。
俺が自分の家族のことについて言うと、ヤエが食いついてきたんだ。
まあ実際うちの家庭環境はだいぶおかしいんだ。
それで、会話の途中で俺は言ったんだよ。
「家から出たい。一人暮らしがしたい」って。
「一人暮らしがしたいの?」
「うーん。一人暮らしじゃなくてもいいな。あの家から出れりゃ、それでいい」
「じゃあ出ればいいんじゃない?」
「簡単に言うなよ。ただでさえ貧乏なのに、俺だけ一人暮らしする金なんてあるわけがない」
「うん、わかってる。私、一人暮らししてるし」
ここで俺は立ち止まった。
押していた自転車が止まって、錆びれたチェーンの音も一緒に止まった。
「本当に一人暮らししてんの?」
「うん。あっ、ほかの人には内緒にしてね」
俺はうなずいて、また歩き始めた。
「あ、でもお金があったら一人暮らししたいってことだよね?」
「まあそうだね」
「じゃあわたしが一生生活に困らないだけのお金をあげるって言ったらどうする?」
「もらうね。迷うことなく」
「本当にあげよっか?」
「おう、くれよ」
中身のないやりとり。少なくとも俺はそう思った。
横断歩道の前で俺とヤエは立ち止まった。青い信号はすでに点滅し始めていた。
「いいよ、あげる」
「マジかよ。でもさすがにタダっていうのはコワイな」
「もちろん条件があるよ」
「一生生活に困らないだけの金をくれる条件って、どんなのだよ」
「私を殺してくれない?」
信号が赤に変わる。人の群れが皆、立ち止まって一瞬だけ時間が停止したような錯覚を覚えた。
そこから俺はとりあえず理由をたずねてみた。
俺はヤエのことを詳しくは知らない。
けれど『自分を殺してくれ』なんて冗談でも言う人間ではないはずだ。
死にたくなるような大きな悩みがあるのかもしれない。
そう思って理由を聞いてみたはいいものの、彼女は、
「悩んでることはないかな。少なくとも死にたくなるような悩みはね」
「動物って本能的に生きようとするでしょ?」
「私の場合はその逆。本能で死にたいって思うの」
「……って、言ってもわかんないよね?」
逆に聞きたい。そんな言葉だけを聞いて理解できる人間がいるか?
途中からヤエの言葉は、霧のように俺の耳を横切るだけだった。
なんとか彼女の言葉を理解しようとして、俺は彼女の唇の動きを見つめた。
白すぎる肌は赤い唇を際立たせて、俺に病的な印象を与える。
頭の中がこんがらがっていた。ふと、人の気配が俺を横切る。
視線を前に向けると、信号はいつの間にか青に変わっていた。
ふと思いついたことをそのまま口にした。
「とりあえずふたりでどこかに遊びに行こう」
予想通り、ヤエは首をかしげた。
自分でもどうしてそんなことを口走ったのか、その時点ではわからなかった。
だけど思い返せば、理由は簡単だった。
単純にヤエとより会話をして、彼女がなにを考えているのかを知ること。
さらに、俺は彼女のことがどちらかと言えば好きだった。だから理由をつけてデートに誘おうとした。
ただそれだけのことだった。
彼女がどうしてそんな話になったのかと聞いてきたけど、俺は無理やり言いくるめた。
俺は彼女の言葉をまったくの嘘だとは思っていなかった。
だから俺は、もしヤエが本気で死にたがっているのなら。
俺が彼女の生きる希望になればいいんじゃないかと、本気でそんな思い違いをしていた。
結論から言えば、彼女はなにも嘘をついていなかった。
ただ本当のことを淡々と述べていたにすぎなかった。
それでも言い訳させてほしい。
信じられるか?
いきなり殺してくれとか、自分は死なないとか。
そんな言葉を鵜呑みにできるほど、俺は無垢じゃなかった。
◆
「ただいま」
玄関のドアを開く。鼓膜を引っ掻くような蝶番の悲鳴に俺は顔をしかめた。
「おかえり」と婆ちゃんのしゃがれ声が居間から聞こえてくる。
靴を脱いで家へとあがる。床がミシミシと音を立てる。
俺はこのボロすぎる一軒家が嫌いだ。
日当たりが極端に悪いこの家は、一年中空気が湿っていてどこかカビ臭い。
風呂の浴槽は今どきステンレスだし、ゴキブリが天井から降ってくることだって珍しくない。
身内で建てたという古い家は、月日の流れとともに建て付けが悪くなったのか、あちこちで不愉快な音を立てた。
「今日はけっこう早く帰ってきたね」
ソファにもたれていた婆ちゃんが、テレビを見ながら言った。
「まあね。ちょっとやらなきゃいけない宿題があって」
「そう」
婆ちゃん、なんて呼んでいるが血のつながりはおそらくない。
おそらく、というのは俺が正確にこの人について知らないから。
「なんか食べる? 昨日の残りの煮物があるけど」
そう言ったのは、台所で洗い物をしていたおばさんだった。
この人についても、俺は詳しく知らない。
母親が子どもの頃にお世話になった人ということ以外知らない。興味もなかった。
「母さんは?」と俺が聞くと、おばさんは、
「夜勤明けで二階で寝てるよ。さっきまで起きてたんだよ」
二年前から俺と母親はこのボロ小屋で、この人たちと住み始めた。
俺の母親は、俺が小学校に上がるまでに二回は離婚している。
いや、ひょっとしたら一回かもしれない。でも、別れた男は間違いなくふたりだ。
男運がないのか、母に問題があるのかそのへんは定かではない。
俺には聞く勇気がなかったし、母親も俺になにも教えてくれなかった。
まあひとつ確かなのは、とにかく金に困り続ける人生だったってことだ。
俺は五歳になるまで保育園に行った記憶がない。
託児所に預けられていた記憶はある。
あと、たしか一時期はおばさんの家に預けられていたはず。
やっぱりここらへんも記憶が曖昧だ。
でも、幼い俺が母親とおしゃべりする時間は決まって夜中だった。
それだけは間違いない。
とにかく母親が男と結婚、あるいは付き合うたびに、住む環境がころころ変わった。
「一人目のアイツは最悪だったわ。ケチだし器は小さいし、ひとりぼっちだったあたしにつけこむし」
いつかおばさんたち相手に愚痴っていた内容がこれだ。
「しかもあたしがほかの男と結婚したら、養育費払わなくなるし。
ほんと、恋愛って結婚できる年齢になる前に経験しておくべきだわ」
「恋愛とバイトだけは、社会に出ていく前にしておきなよ」と昔からよく母に言われた。
俺が父親と認識していた男と、母親がわかれたのが小学五年生のとき。
これ以来、母親は男と付き合うのをやめた。もしかしたら母は男性不信のようなものに陥ったのかもしれない。
とにかく母親は金がないとしきりに俺に愚痴った。結局母が昔育ててもらったという老夫婦の家に転がりこんだ。
三年以上、俺の住む環境が変わらなかったのは、これが最初で最後のはずだ。
もっともこの生活も、おじさんが奥さんを失って、切り盛りしていた定食屋を畳んで終わった。
呆れたことに、おじさんは俺たちと住んでいた家を売って蒸発しやがった。
なにが呆れるってその売った家でできた金が、四百万にもならなかったってことだ。
きちんとした業者を通さずに、日曜大工でできた家だからだ。
オンボロの軽自動車と一緒に消えたおじさんの行方はわからない。
しかし、おじさんの残り少ない人生が破綻するということだけは、馬鹿な俺でも理解できた。
まあそんなこんなで、今の家にたどり着いた。
父親が何回かかわったせいで、俺は親戚の関係を把握できていない。
苦労をしたのかと聞かれたら、ピンとこない。
みょう字が変わったとき、何回か自分の持ち物に書いてあった名前を消す作業がめんどくさかった。
それは明確に覚えている。
だけど俺は普通に学校生活を楽しんでいたし、転校してもなんだかんだ友達に困ることもなかった。
昔から周りの環境が変わることに、慣れていたからかもしれない。
俺は学生カバンをソファの片隅に置いて、ばあちゃんとおばさんを見た。
昔は個人で服屋を開いていたおばさんは、株かなにかでほとんどの金を失ってうつ病になったらしい。
結局店も家も売って、最終的に俺たちと同じようにこの家に住むことになった。
ばあちゃんは、インシュリンがなきゃ生活できないが、土日はよく出かけている。
少なくとも、今の母の人生よりは充実しているだろう。
この人たちはなんで生きてんだろ?
そんな疑問が湧いて、俺はちいさくため息をついた。
よくわからない関係の人たちと住むのだけは、未だに気持ちが受け付けなかった。
この家のなにもかもが嫌いだ。
匂いも。
音も。
ご飯も。
家具も。
人も。
『わたしを殺してくれない?』
彼女の白い顔と赤い唇が浮かんだけど、俺はすぐにそれをかき消した。
今日はここまで
ダラダラと続ける
面白かった
ここ1年くらい小説読んでなかったけど今日、小説を読もうと思いました
ありがとー
今から読む
うまっ!
ありがとう
>>1さんの文面白いです
wktkして待ってます