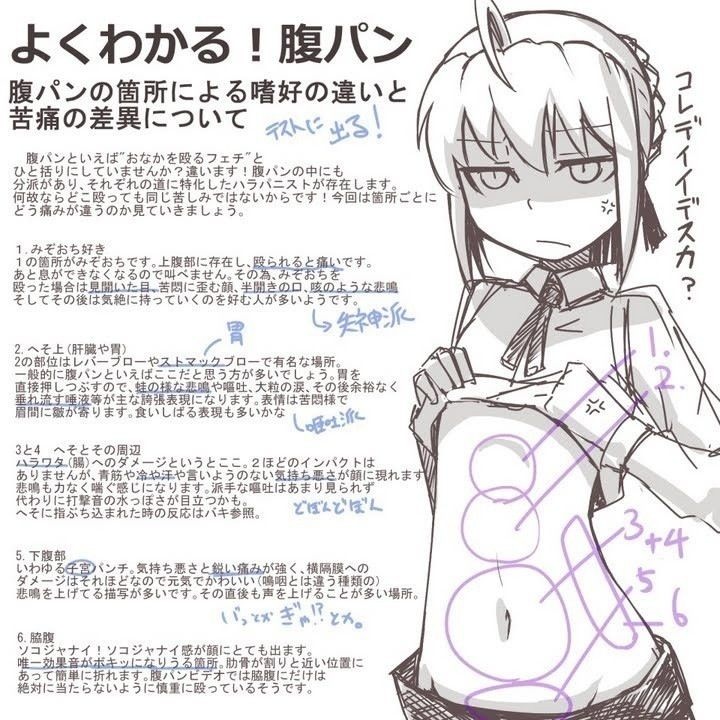兄弟姉妹と気持ちいいことしてる人集まれぇ~!スレより

前回:
vol.1
vol.2
vol.3
vol.4
vol.5
vol.6
vol.7
規制で止まった際は時間を開けてから連投しますのでご了承ください。
それからの一年間、俺は出来るだけバイトを多く入れ、休日もあまり遊びには行かず、たまに妹を映画に連れて行ってやるぐらいにしか金を使わずに貯金に励んだ。
理由は一つ、大学のキャンパス移転に合わせ、三年生から通う新キャンパスの近くにアパートを借りる為だ。
独立して一人暮らしを始める事で、強引に妹との関係を断ち切ろうと考えていた。
俺と妹が血の繋がりのある兄妹である以上、この関係を続けていてもお互いの人生に幸せがもたらされることは無い。
今ならまだ引き返せる。
関係を断ち切り、ほとぼりが冷めた頃に会えば、俺たちはまた兄妹に戻れる筈だ。
そう信じていた。そう信じたかった。
しかし、心ではそう決心しても、日に日に女らしくなっていく妹の肉体の魅力には抗えず、相変わらず週に二~四回ぐらいのペースで肌を合わせていた。
少女から女性へと成長しつつある妹の裸身を想いのままに出来る夜は、俺にとって何よりも楽しみだった。
俺は妹に風呂桶の淵に手を付かせ、尻を突き出させると、まるでバックから犯すような格好で妹の性器に俺のペニスを擦り付けていた。
クチュクチュと淫らな音が妹の股間から聞こえる。
張りのある尻をぐっと掴み、犯したい気持ちをぐっと堪えてひたすらに腰を降る。
「Y香、いいよ……すげぇ気持ちいい」
「うん、あたしも……いい、すごく、あん、いい……」
俺は妹の裸身を後ろから抱きしめ、少しでも長持ちさせる為に腰の振りのグラインドを大きくするが、
ボディーソープに塗れた二人の身体はヌルヌルと滑り、その感覚が性感と興奮を更に倍増させる。
「ん……お兄ちゃん、好き……」
妹が上体を捻りキスをせがむ。
「Y香、俺もだよ」
俺も顔を近づけ、妹の唇を吸い、舌を絡ませ、唇を押し付け合う。
口と性器と両方の粘膜を擦り付け合えば、お互いに急速に高まっていく。
「お兄ちゃん、来て!いっぱい出して!」
「う、くッ!」
俺は妹の裸身を抱きしめながら、妹が俺のペニスの先端に被せてくれた手の平の中に精を放った。
ドクッ、ドクッとペニスが脈打ち、白くこってりとした粘液が妹の股間と手の平を汚した。
「凄い……いっぱい出たね」
妹は両手で俺の精液を弄ぶと、その一番濃い部分を指でつまみ「あーん」と言いいながらパクリと口に入れた。
口の中で舌で転がし、ニチャニチャとその食感を楽しむと、ゴクリと飲み込んだ。
俺は妹の股間からペニスを離し、お湯を汲み、妹の手と股間を流してやる。
排水溝へと流されてゆく俺の精液を名残惜しそうに眺めている妹をギュッと抱きしめ、びっくりした顔の妹の唇に強く吸い付いた。
この頃の俺は、射精を果たすととにかく妹が愛おしくなり、夜の行為の締めは必ず長いキスだった。
妹も「最近お兄ちゃんが情熱的に抱いてくれてすごく嬉しい」
と、より一層フェラチオや手コキを熱心にしてくれるようになっていた。
しかし、妹を抱く度に(この関係もあと少しだ)と、そう自分に言い聞かせていた。
そう思えば思うほど、妹の裸体を隅々まで楽しみたい欲求に駆られる。
現に今のバックでの素股の時でさえ、何度(このまま挿入したい……!)と思ったか知れない。
しかし、「それ」をしてしまえば、俺たちは決定的に戻れなくなってしまう。
俺はその想いを「妹をキズ者にしてはいけない」という使命感にすり替え、なんとかやり過ごしていた。
母が美容院の店長たちとの飲み会から帰ってくるまでにはまだ時間がある。
俺は妹を風呂桶の縁に座らせると。
「俺ばっかりイッちゃ悪いもんな」
と妹の股間に顔を埋め、尖らせた舌先でクリトリスを舐め上げた。
「あんっ、あぁっ!」
妹の甘く切ない喘ぎ声が、風呂に響き渡った。
F実さんは母と美容室の店長が都内の美容室で修行していた時代の一番若い後輩で、なぜか母や店長とウマが合い、今でもウチや店長とは家族ぐるみで付き合いがある。
子供の頃から何度もウチに遊びに来たり、父がいない日には泊まりがけで遊びに来たこともあり、俺たち兄妹にとっても姉のような存在だ。
(端折ってしまったのだが、夏祭りの日に俺の眉毛や前髪を整えてくれたのもF実さんだ)
F実さんは母同様、普段は同じ美容室に不定期で入りながら、都内のお店時代に馴染みになった個人のお客さんのメイクやスタイリングも手掛けている。
スラッとしたスレンダーな体型に金髪のショートヘアがよく似合う、キリッとした印象の大人の女性で、妹も常々「F実さんみたいにカッコいい女の人になりたい」と言っている。
「ねぇY希くん、一眼レフ買ったんだって?ちょっと見せてよ」そう言ってメンソールの煙草を灰皿で揉み消すと、F実さんは鞄を置きに部屋へ行く俺の後に着いてきた。
「二階はY希くんとY香ちゃんしか使ってないんだって?完全に二人のお城じゃん、いいなー」
F実さんの何気無い一言に、俺は一瞬ドキっとした。
俺の部屋に入り、一眼レフを渡すと「へー、なかなか良いの買ったねぇ、カメラマン目指してんの?」
と言いながらあれこれ弄り始めた。
「それは趣味の延長みたいなもんすね、まぁ映像関係の仕事ができればいいなとは思ってますけど」
「そっかー、お兄ちゃんは結構堅実なんだね」
そう言うとF実さんは俺にカメラを向けた。
「ねぇ、Y香ちゃんとはどうなってんの?」
「 はぁ!?」
突然の質問に、俺は心臓が止まるかと思った。
「あたしさ、Y香ちゃんが小学校の頃から、ずっとメル友なんだよね。なんか結構悩み多き乙女じゃない、Y香ちゃんって。あたし結構相談に乗ったりしてんだよね」
なんてこった、そんなの初耳だぞ。
「うん、だいたい聞いてるよ」
おいおい、何やってんだあのバカ。
「ま、あたしは君たち兄妹とはちょっと形が違うけどさ、好きになっちゃいけない相手って、いるよねー…」
F実さんの口調は軽かったが、言ってる内容はそこそこヘビーだった。
「これが片思いだったら、自分の価値観ごと諦めちゃえるかもしれないんだけど、下手に両思いだったりすると、余計に拗れちゃうんだよね……」
F実さんは、俺のカメラを弄りながら、下を向いて寂しそうに話はじめた。
ここの話は長いので端折るが、要するにF実さんは「女性として、同じ女性を恋愛対象として愛する」という性別的価値観の持ち主だった。
妹がF実さんに俺への想いを相談した時に、アドバイスがてら秘密を共有して以来、妹とF実さんはお互いに信頼できる相談相手として、連絡を取り合っていたらしい。
F実さんは、静かだが力強い口調でそう言うと、俺の一眼レフを俺の机の上に置いた。
「Y香ちゃんは本気だよ。まだ十代だけど、あの子の頭の良さは半端じゃないのはY希くんだって解るでしょ?
ちゃんと物事を考えて、冷静に判断して、それでも尚はっきりとあたしに言うんだよ、『お兄ちゃんを男として好き』だって。あたしは、Y香ちゃんの言う事が単にお兄ちゃんへの憧れとか、幼さや未熟さだけで言ってるとは思えない。
あたしだって何度も聞いたよ、でもその度にY香ちゃんは中学生とは思えないような文章であたしにお兄ちゃんへの想いをぶつけてきたんだ。
『パパとママには何て言って良いか解らないけど、いつか必ず解ってもらう。その為に、進路のこともちゃんと考えてる』って。だからあたしは信じることにしたんだ、これは本気だって」
やっぱり、妹の成績や進路へのこだわりは俺たちの関係を両親に認めてもらうためのものだったのか。
けれど、これは倫理の問題だ。
いい成績を取ったから、いい学校に入って、いい企業に就職できたから許されるような話じゃない。
何があろうと、血の繋がった兄妹同士で愛し合うなんて許される筈がない。
それは、俺たち四人の家族の関係を壊してしまうことにも繋がりかねない問題だ。
万が一両親が俺たちの関係を認めたとしても、法律上結婚することはできないし、それらを無視して子供を作ったとしても、遺伝子的なリスクが高く、どの道俺たちが幸せになんてなれないことは、今の時点ですでに解りきっているのだ。
それが、俺たちの、何よりY香の為なのだ。
解っている、解っているのだ。
俺だって、自分の事より妹の事を大事に思っているからこそ、苦しいのだ。
俺は何をやっているのだろう、よりによって世界にただ一人の、かけがえの無い妹に、何て事をしてしまったのだろう。
絞り出すように、F実さんに自分の胸の内を吐露していた俺の目から、自然に涙が溢れていた。
「Y希くん……」
F実さんは、何も言わずにただ俯いて涙をこぼすだけの俺をそっと抱きしめてくれた。
暫くして、階下から妹の声が聞こえた。
進学コースの授業内容についていくのはそれなりに大変らしく、いつもは暗くなるまで学校の図書室や教室で勉強してかえるので帰りの遅い妹も、母からF実さんが来ていることを聞いたのだろうか、今日はいつもより早めに帰って来たのだ。
空けっぱなしのドアのすぐ向こうから、妹のご機嫌な声が聞こえたが、F実さんの声とともにすぐに妹の部屋へと消えていった。
俺は涙を拭い、一階の洗面所に降りて顔を洗うと、またすぐ部屋に戻り、少し寝た。
夕食を食べ、暫くするとF実さんは帰ると言うので、俺が駅まで送っていくことになった。
こうなると当然「お兄ちゃんだけずるい。あたしも行く!」となり、妹も着いてきた。
駅までの道では本当に他愛もない会話しかしなかったのだが、駅での別れ際、F実さんは俺達二人をギュッと抱きしめて「あたしは、何があってもあんたたち二人の味方だからね。もしものときは、あたしがご両親を説得するからね」といってくれた。
その手は強く温かく、少しだけ、俺の心をほぐしてくれたような気がした。
「はい。がんばります」
妹は目を真っ赤にし、やや上ずった声できっぱりとそう言い切った。
俺は、ただ「ありがとうございます」としか言えなかった。
春の終わりだというのに、その日は妙に肌寒く、妹は「寒い寒い」
と言いながら、俺の腕にしがみつくように腕を組んできた
「そうだな、寒いからコーヒーでも飲んで行こう」
そう言って、駅の近くのファーストフード店に入った。
人気のないファーストフード店の二階には俺たちの他に客はほとんどおらず、二人だけの話をするにはもってこいだった。
「F実さんと話したんだね、あたしたちの事」
「あぁ、お前がF実さんにずっと相談してたなんて全然知らなかったよ」
「あたしだって、なんにも悩まないじゃないもーん」
そう言って、妹はカフェオレを一口啜った。
俺も黙ってコーヒーを一口啜り、そして意を決した。
「Y香、俺三年生になったら一人暮らしするから」
「え?」
「キャンパスがさ、変わるんだよ。少し都心寄りになるんだけど、ここから通うんじゃちょっと電車が面倒でさ、だからアパート借りようと思ってるんだ」
「××区」
「あ、そこあたしの友達が住んでる所だよ。たしかにあそこ電車不便だよね」
「うん、だから、卒業まではそこで暮らす。一人で」
「うん、わかった」
「わかったって、お前」
「だからわかったって。そう言ってんじゃん」
「いやだからお前何をどう」
「距離を置こうってことでしょ?あたしにだって解るよそんな事。だって今のままじゃあたし達ほんとヤバいもんね。
だってもうエッチな事するの当たり前になっちゃってるじゃん。しかも超気持ちいし、楽しいし。兄妹なのに、ヤバいってホント」
わざと軽い調子を装っていることが一発で解る、バレバレの演技だった。
俺は何も言えず、気まずい沈黙が二人の間に流れた。
「……お兄ちゃんが悩んでるの、Y香だって知ってるし、Y香だって、お父さんとお母さんになんて言ったらいいか、正直まだ解んないよ。世間的にも、法律的にも許されないことも知ってる。
でも、だからって、あたし諦めたくないもん。こんなに好きな人の事、愛し合ってる人の事、簡単に諦められないもん!」
妹の目からは今にも涙が零れ落ちそうだった。
というか、その資格がなかった。
「でもね、お兄ちゃん、Y香、後悔なんかしてないよ。
法律じゃ認められてないかもしれないけど、でも、あたしはお兄ちゃんとどっか遠くに行って、誰もY香とお兄ちゃんの事知らない土地に行って、二人で暮らしたって良いって思ってるよ?お父さんとお母さんには悪いけど、あたし、お兄ちゃんの為なら……」
「Y香!」
思わず大きい声が出てしまった。
窓際の席でイヤホンをして勉強中の学生らしき人が振り返り、またすぐにノートに向かうのが視界の隅に見えた。
妹が突然の大声にびっくりした顔で俺を見つめている。
「ダメだY香。それ以上は、何があっても言っちゃダメだ」
妹に親を捨てさせるなんて絶対にさせちゃいけない。
消えるのは、俺一人でいい。
「悪いのは、俺なんだ。だから責任は全部俺が取る」
「責任とか言わないでよ」
「ちゃんとって何?お兄ちゃん何かY香に悪いことしたの?Y香、そんなこと全然思ってないよ?初めてキスした時も、フェラチオした時も、裸で抱き合った時も、全部嬉しかったもん!お兄ちゃんに愛されて、幸せだったもん!」
「Y香、声大きいって」
「……Y香は、今でも、すごく楽しいし、すごく幸せだから。だから後悔なんてしてないよ」
正直言って、そうきっぱり言い切れる妹が羨ましかった。
とても眩しく、同時に嬉しくもあった。
俺たちのこの関係が、妹の負担や心の傷になっていないことが何より俺の救いだった。
「……お兄ちゃんがどうしても距離を置きたいって言うなら、Y香、止めないから。Y香だって、お兄ちゃんに今まで随分ワガママ言ってきたし、Y香だって、ちゃんと解ってるから。
気持ちでは納得してないけど、理屈では解ってるから。もしY香がお兄ちゃんの立場だったとしたら、そうすると思うし。お兄ちゃんの事、恨んだり、責めたりはしないから」
「あぁ、……ありがとな」
「ううん、全然」
それきり、俺たち兄妹は黙ってコーヒーとカフェオレを飲んだ。
「あ、あれお父さんじゃない?」
妹も気付いたようだ。
「よし、じゃあ三人で帰るか」
「うん」
そう言って、妹は紙コップを二つ持って立ちあがった。
小走りで階段を降り、閉店作業間際のファーストフード店を飛び出し父を呼びとめる。
さすがにこんな時間に高校生の娘と出くわすとは思ってもいなかった父が目を丸くしている。
やがて遅れて店を出る俺の姿も見付けた父がゆっくり歩いてくる。
「今日は冷えるな、お前ら風邪引くなよ」
「大丈夫だよ、お兄ちゃんがカフェオレ奢ってくれたから」
まだ肌寒さの残る晩春の夜道を、父と妹の後ろを歩く俺の胸の内には、店を出際に妹が耳元で囁いた一言が渦巻いていた。
「お家出ていく前に、Y香の処女だけは貰ってね」
支援してくれた方々、毎回ありがとうございます。